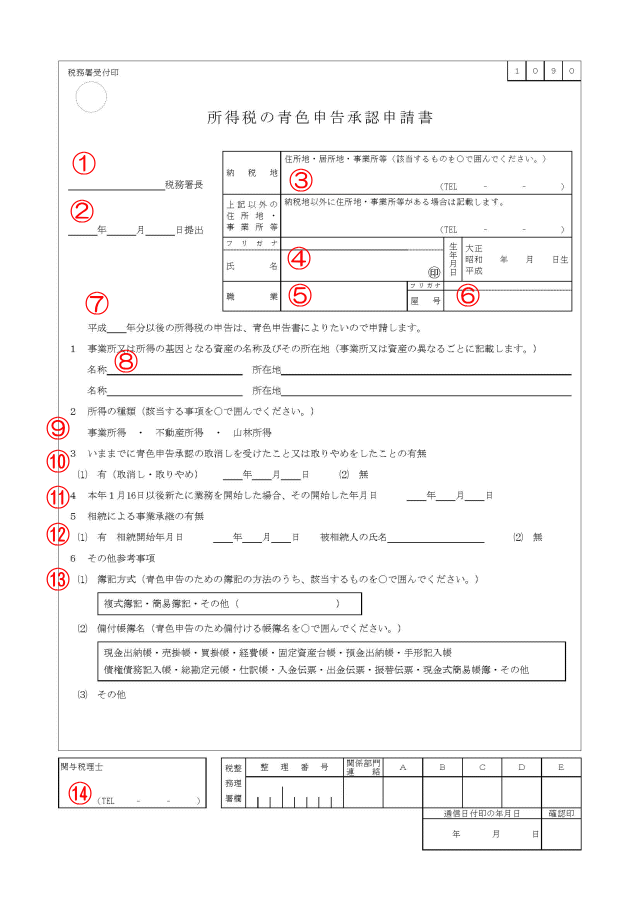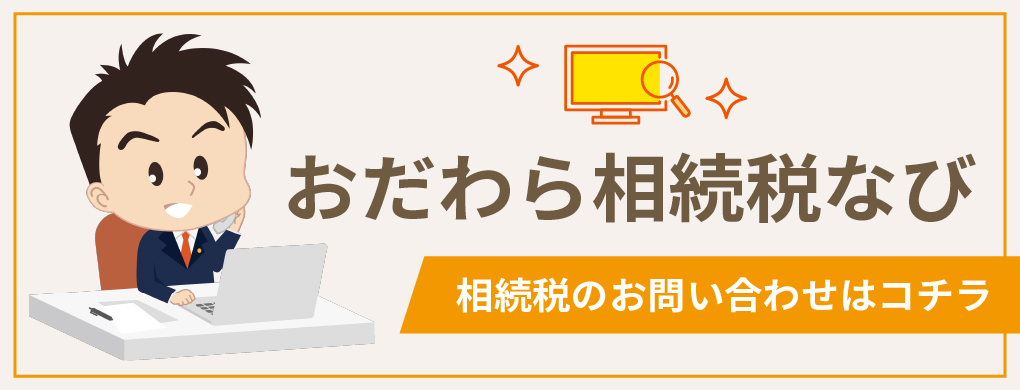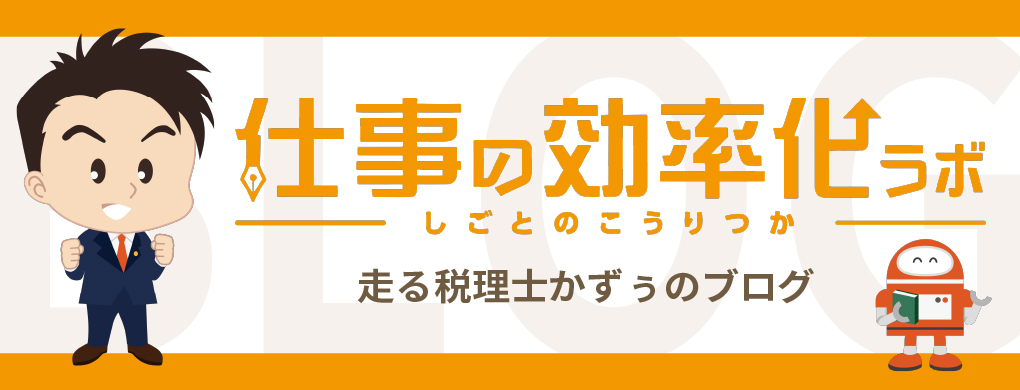青色申告の特典を受けるには届出が必要です!
もう申告手続きは終わっていらっしゃいますか?
まだ終わっていないという方は、そろそろ重い腰を上げないと間に合わない時期になってきましたよ~(・_・;)
さて、平成26年分の申告期限は3月16日(月)までですが、今年から「青色申告で手続きしたい!!」という方も3月16日までに税務署に届け出をしなければなりません。
青色申告にはいろいろな特典がいっぱいです!
青色申告のメリット・白色申告にメリットはない
それでは青色申告を受けるために、具体的にどのような手続きや書類が必要になるかをおさらいしておきましょう!
青色申告には「青色申告承認申請書」の提出が必要!
青色申告を受けるためには「青色申告申請承認書」の提出をしなければなりません。
この申請書の提出があってはじめて65万円控除などの特典が受けられるのです。忘れずに提出しましょう。
青色申告申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は次のようになっています。
① 個人事業を開業したとき(事業や不動産収入がはじまったとき)・・・事業などを開始した時から2ヶ月以内
② その年から青色申告の適用を受けようとするとき・・・その年の3月15日まで(15日が土日の場合にはその次の月曜日まで)
※相続により事業を引き継いだ場合には、若干期限が変わってきますのでご注意ください。
要は「青色申告をしたい場合には事前に届け出を出しておかなければならない」というコトです。
今回の確定申告(平成26年分)の処理をしているときに26年分から青色申告をしようと思ってもできないということ。
前もってちゃんと準備をしておかなければなりません。
来年も同じことを思わないように、早目に青色申告承認申請書を出しておくようにしましょう。
提出先は納税地の税務署へ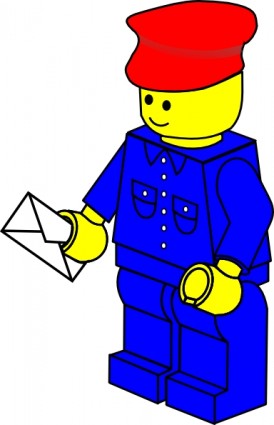
青色申告承認申請書は、納税地(基本的には住所のある場所)を所轄する税務署へ提出します。
ちなみに小田原市や南足柄市など、県西地域二市八町の所轄税務署は小田原税務署です。
提出方法は直接申請書を持っていく方法のほかに郵送や電子申請でも可能です。
この時期の税務署は非常に混んでいるので郵送してしまった方が得策かもしれません(-_-;)
郵送の場合には、提出用と控用の二部を作成し返信用の封筒に切手を貼って同封してください。
提出用に必要事項を記入した後、それをコピーして控にしてしまえば簡単です。
郵送の場合、締切日(今年は3/16)当日の消印があればギリギリセーフですが、できるだけ余裕をもって提出するようにしてくださいね。
申請書は国税庁のホームページからダウンロード
青色申告申請書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。
こちらのページから申請書をダウンロードしてプリントアウトしてください。
申請書には次の事項を記載していきます。
① 管轄の税務署
納税地の税務署の名前を記載します。(例:小田原税務署など)
② 提出日
「青色申告申請承認書」を提出する予定日を記入しておきます。郵送の場合は記入した日で結構です。
③ 納税地 (住所地・居所地・事業所等)
住所地・居所地・事業所のいずれかに○をします。
原則は住所地になりますので住所地に○をしておけば大丈夫です。
その下の「上記以外の住所地・事業所等」と記入する欄には、住所以外にお店や事務所などを有している場合に記載してください。
無ければ空欄で問題ありません。
④ 氏名、生年月日
自分の氏名とフリガナ(カタカナ)、生年月日を記載します。
印鑑は認印でも何でもかまいません。
⑤ 職業
職業を記入します。個人事業の方であれば具体的な事業内容を、サラリーマンの不動産所得なら「会社員」と記載しましょう。
⑥ 屋号、フリガナ
屋号がある方は記入します。(○○美容室、××商店など)
特にお店の名前が無い方やサラリーマンの方は空欄でオッケーです。
⑦ 平成 年分以降の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。
空欄に青色申告を開始する予定の年を記入します。
⑧ 事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地
個人事業の方はお店や事務所の名前と住所を記載します。
自宅がお店や事務所と兼用の場合には、所在地に自宅の住所を書きます。
不動産所得の人は、アパートの名称や住所を記載します。
⑨ 所得の種類
事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかに○をします。
該当するところに○を付けて下さい。
⑩ いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
特に問題なければ「無」のところに○を付けます。
⑪ 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
既に開業していて白色申告だったものを青色に変える方は空欄で大丈夫。
今年から新たに事業などを開始した場合で事業開始が1月16日以降であれば、事業を開始した日を記入します。
※2ヶ月以内に申請することを忘れないように!
⑫ 相続による事業承継の有無
特に問題なければ「無」のところに○を付けます。
⑬ その他参考事項
▼簿記方式
せっかく青色のメリットを受けるのであれば、65万円控除を受けることができる「複式簿記」を選びましょう。
※ 簡易簿記の場合、貸借対照表を作成できないので特別控除は10万円になってしまいます。
▼備付帳簿名
簡易簿記なら現金出納帳のみでかまいませんが、複式簿記の場合には最低でも「総勘定元帳」はチェックしなければなりません。
あとは必要に応じて仕訳帳や売掛帳、買掛帳なども作成しましょう。
※ この情報は参考事項なので、ここで簡易簿記に○を付けても、実際に複式簿記で帳簿を付ければ65万円控除受けることはできます。
⑭ 関与税理士
税理士にお願いしている場合には記載しますが、自分自身で提出する場合には空欄でオッケーです。
簡単に作成できる書類なので是非期限までに提出してくださいね(*´з`)