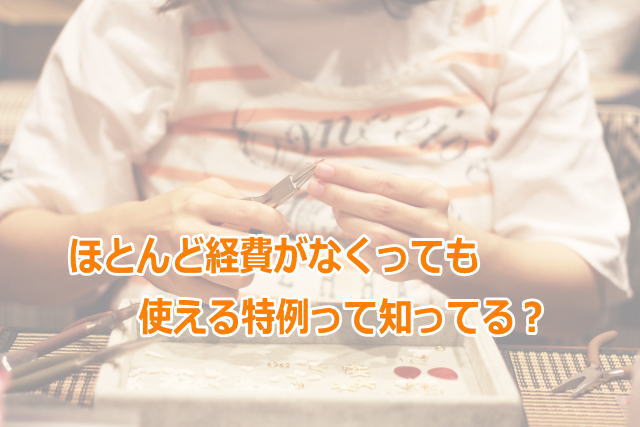
実際の支払いが無くても経費が認められる裏ワザ?~家内労働者の特例~
「収入はあるんだけど経費にできるようなものってあんまりないんだよね~」
アフィリエイターやピアノの先生など、収入はそこそこあるけど経費になるようなものがほとんどない仕事って結構ありますよね。
ピアノの先生や保険の外交員、シルバー人材センターなどの収入は経費というものがほとんどかかりません。
ただ雇われているわけでは無いので、こういった収入はお給料ではありません。
個人事業主として、ある程度の収入がある人は確定申告をする必要があるんですね。
こういった収入って、そのまま税金の対象となってしまうのでしょうか?
実はこのようなお仕事の方のために設けられている税金の特例があるんですよ。
その特例が「家内労働者等の必要経費の特例」というもの。
この特例を使えば、実際に支払った経費が無かったとしても、有利に税金を計算できる可能性があるのです!
家内労働者の必要経費の特例とは?
個人でビジネスをしている方は確定申告をしなければなりません。
このときの税金計算の基本となる所得というものは、
仕事の収入 - 仕事の必要経費 = 所得
という計算をします。
この必要経費が多ければ所得も少なくなるので税金が少なくなるというコトになります。
もちろん仕事の必要経費は、実際にお金を払ったものであるということが大前提であるのは言うまでもありません。
ただ、ある特定の働き方をしている人には「実際にお金で払ったものではなく、ある程度までは経費にしていいよ」という特例があるのです。
それが「家内労働者等の必要経費の特例」です。
この特例の内容とは、実際にかかった必要経費が65万円未満であった場合には、最高65万円までは必要経費として認めてくれる制度なのです。
必要経費が65万円未満であれば、使っていない金額であっても経費として認めてくれる特例なのでオトクですよね。
この特例を使うにはちょっと条件があるのでチェックしましょう!
ただ、この家内労働者の特例を受けるためには一定の条件が必要です。
それ条件とは「家内労働者等」というものに該当すること。
家内労働者とは、
「家の中で働く人」= 要は「内職さん」のコト
というものを前提としています。
お家の中でコツコツとネジをはめたり箱を組み立てたり・・・というようなイメージですね。

ただそれでは限定的すぎるので、家内労働者「等」ということにして、すこし枠を広げています。
「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」
ということになっているんですね。
この要件に該当するためのポイントは3つです。
① 特定の人を対象としている・・・請負先が特定されていること(不特定多数ではない)
② 継続的に行っている・・・スポット案件ではない
③ 販売ではなくサービスである
この3つの要件を満たしているかどうか・・・ということがこの特例が使えるかどうかの判定材料です。
大手教室の先生はOK、自宅で教える個人レッスンはNG
具体的な例で考えてみましょう!
自宅でピアノ教室をしている先生は特例は使えません
この特例の3つのポイントのうち、1番大事なのは「①特定の人が対象」というところなんです。
要は「サービスを提供している相手が特定のお客様である」というコト。
逆に言えば、不特定多数の人を対象としたサービスを提供する場合はNGなのです。
例えば、弁護士、税理士のように事務所を開いていたり、学習塾で広く生徒を集めたりしているような場合はどうでしょう。
こういった業種は、常に同じ人ではなく、不特定多数の人向けにサービスを提供しています。
ですので家内労働者の特例は受けられません。
仮に「特定の人しか相手にしていないよ~」と言っても、広くお客様を募集している段階でNG。
自分のお店や教室、オフィスをもっている・・・という状態であれば広くお客様を募集していると考えられてしまうのです。
ですから自宅の一室でピアノの先生をしている人については、「自分の教室で生徒を募集している」ということになるので、この特例は適用できません。
「教室を持っています」ということは、色んなところから生徒を集めていると考えられてしまうので、特定とは言い切れなくなるのですね。
特定の会社に委託されているヤ○ハの先生ならOK
ただ、同じピアノの先生ですが、ヤ○ハ音楽教室の先生ならこの特例が適用ができます。
(ちなみにヤ○ハ音楽教室の先生は個人事業主です。お給料ではないですよ)
大手音楽教室などの場合には、「ヤ○ハ」という特定の会社に対してサービスを提供しているということになります。
ですので「特定の」という要件を満たすので、この特例が使えるのです。
同じような仕事をしているのに、サービスの提供先ひとつで大きく変わってしまうんですよ。

どんな業種が適用できるのか?
参考までに、この特例の適用を受けられる業種と言うと
▼ 昔ながらの内職さん
▼ 電力会社などの検針員、新聞やNHKの集金、ヤクルトのおばさん
▼ 特定の会社に所属しているピアノ講師
▼ 特定の会社だけのアフィリエイター
▼ ユーチューバー
▼ 特定の生命保険や損害保険の外交員
▼ webデザイナーや翻訳など特定の会社から下請している人
▼ 専属モデルやレースクイーン、セクシー女優さん
などがあげられます。
いずれも「特定の人に」「継続して」「サービスを提供」というところがポイントです。
サラリーマンの副業などとは併用できないので注意
ちなみに「家内労働者等の必要経費の特例」は、お給料から控除できる「給与所得控除」と重複して利用できるのは、両方合わせて65万円までが上限となっています。
例えば、お給料収入が80万円ある人はお給料の方で給与所得控除65万円を使い切ってしまうので、家内労働者の特例は利用できません。
お給料収入が40万円であれば、65万円-40万円=25万円までは家内労働者の特例を利用することができます。
その他にも、例えば雑所得の必要経費がある場合なども利用が制限されます。
公的年金以外の年金(生命保険の個人年金など)の所得計算をする際、収入金額ー必要経費(既払込保険料)などの計算をするのですが、その際に計上した必要経費が65万円を超えてしまえばこの特例は利用できません。
シルバー人材センターなどで働く高齢者に良くあるケースです。
気をつけないと間違えてしまいますので注意しましょう。
青色申告特別控除との併用も可能
ちなみに、この家内労働者の特例は青色申告特別控除(10万円or65万円)と併用することも可能です。
帳簿をきちんとつける、総勘定元帳を作るといった青色の要件を満たせば、最大で家内労働者特例65万円+青色申告特別控除65万=130万円まで控除することもできます。
(ただ、実務的にはそこまでキチンと帳簿を付けているのは、ある程度の規模で事業をやっている方だと思いますので現実的ではないかもしれませんけど)
10万円控除なら比較的簡単に適用できますので、小規模の事業の方なら特例を使うメリットは大きいかも知れませんね。
まとめ
「知らなくてソンした~(ToT)/」と言う方も、申告期限から5年以内であれば再度申告(更正の請求)をすることも可能です。
思い当たる方については過去の申告書を見直してみては?


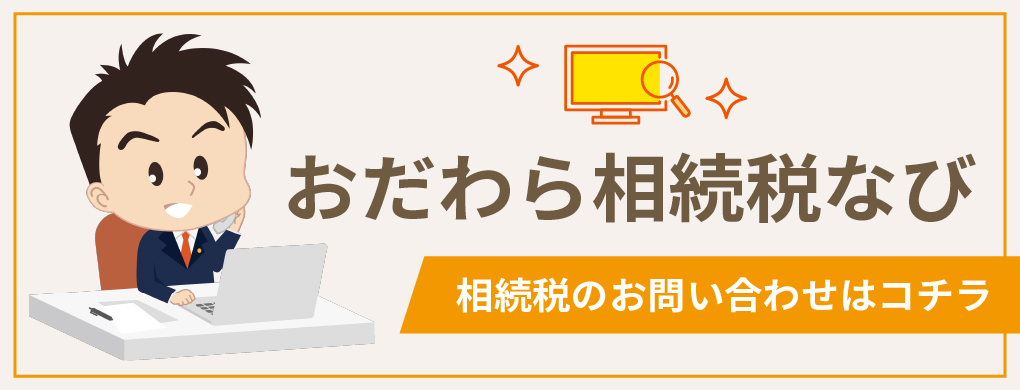
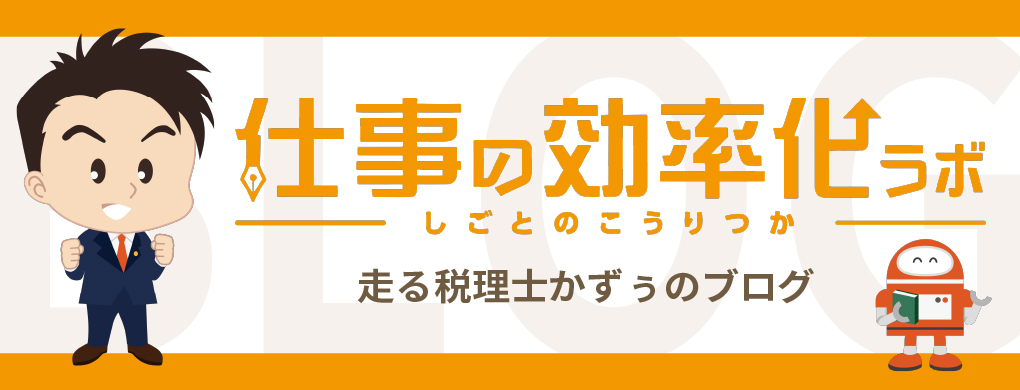
はじめまして!
「特定の人を対象としている・・・請負先が1つだけは」
誤情報ですよ
複数でも(例えば4社など)問題なしですよ~
ありがとうございます!
確かに「1つだけ」というわけではないですね。誤解を招いてすいません…。
家内労働者等の必要経費の特例について
お教えください。
例えば、ピアノ講師としてヤマハで教え、かつ自宅で不特定多数の生徒に教えている場合、(ヤマハで年収50万、自宅レッスンで年収100万)特例の55万は使えますか?
兼業していたとしても一定の条件を満たせば適用することは可能ですね。
(それぞれの収入に応じて必要経費を振り分けるなど)
ただ、ちょっと計算が複雑になるので、実際の処理などについては税務署や専門家にご相談ください!
早速のお返事ありがとうございます。
税務署に相談します。