
お客様の要望にすべて応じることが正解ではない~税理士の決断~
「お客様は神様である」
商売を行っていくうえで、良く考えさせるのが「顧客至上主義」というモノ。
自分の商品やサービスに対してお金を払ってくれるお客様という存在は、とても大切なものであることは間違いありません。
ただ、お客様の要求をすべて満たせばそれで良いかと言うと、決してそういうわけではありません。
理不尽な要求を訴えてくるクレーマーのような存在も少なからずいます。
ビジネスを行う上では「そのような場合にどのような対応をとるのか?」ということは考えておかなければなりません。
われわれ税理士のような法律の専門家も、例え法律的・判例的な根拠に基づいて処理をしたとしてもクライアントから訴えられるようなケースもあります。
そのような場合にどのように対応すべきなのか。
ちょっと考えさせられる事例がありますのでご紹介いたします。
具体的な事例
【平成26年4月25日東京地方裁判所判例より】
※この事例は相続税申告について、相続人(納税者)が課税庁(国税)の処分を取り消すように訴えた判例です。
被相続人が父親、相続人を母親、長男、次男及び長女の4人とする相続税申告書が平成22年2月に提出。
1年後の平成23年2月に相続人の一人である長女が、申告した相続財産のうち、「子供名義の定期預金」は、生前に贈与を受けているので相続財産ではないという更正の請求(還付申請)を行った。
これに対して、国税側は更正をする理由が無い(還付しない)という処分をした。
これに対して、長女はその内容を不服として処分取り消しの訴えを起こしたという内容。【主な流れ】
▼長男は、平成22年1月半ば、相続人全員の相続税の申告をA税理士に依頼したが、相続税の申告期限までは1ヶ月しかない(時間的余裕がない)。
▼長男が、父親の財産と別に保管されていた「子供名義の複数の定期預金証書」を「発見」し、A税理士に報告
▼A税理士は、財産の管理状況から、それらの定期預金を「名義預金」として相続財産として申告することを勧める
▼長男は長女にその旨を電話で報告。長女は約30年前から父親に定期預金の存在を教えてもらっており「何をばかな」と逆上。
▼長女は、A税理士に法律上の根拠等について質問。A税理士は平成22年2月中旬に一方的に長女の申告代理を辞任。【長女の主張】
▼申告期限まで数日しかない。全ての書類を書き換えて相続税の計算は不可能。
▼一旦A税理士の内容で申告納税して、後に更正の請求をするという方法を選択。
▼長女以外の相続人も、長女と同様に父親から生前贈与を受けていたが、A税理士の機嫌を損ねることを恐れ更正の請求はせず。
▼長女以外の相続人も、父親から贈与を受けていなかったから更正の請求をしなかったわけではないと主張。
【裁判所の判決の要旨】
裁判所の判決は「A税理士が行った処理は妥当であり、長女の請求は棄却する」という内容でした。
▼父親から子供に対して贈与があったと客観的に証明する「贈与証書のような書類」はない。
▼名義の変更(父→子)はあったが、預金証書自体は父親が保管していた。
▼上記のことから、直ちに財産を贈与するという確定的な意思があったわけでは無い。
▼従って、A税理士が「名義預金」と指摘して相続税の申告を行ったのは正に妥当な処理である。
▼長女は、「一旦申告納税して、後に更正の請求をする」と言及した割には実際に更正の請求をするまで1年以上かかっている。
納税者の希望を通すことが税理士の仕事ではない
そもそも私たちは法律や判例に基づいて、お客様の申告などの手続きを行っています。
勝手に自分たちの判断や好き嫌いで処理をしているわけではありません。
「税金なんて払いたくないから、払わないで住むような申告書を作成して!」
なんて言われても、そんな処理をすることなんてできません。
もちろん、法律的に払わなくて済むような特例や優遇措置などがあれば、こちらからキチンとご提案をして一番有利な方法を選択できるアドバイスをします。
個人事業や小規模な会社であれば、その方たちが一番メリットを享受できるような方法を選択します。
相続であれば、税金だけでなく遺された方が一番幸せになれるような財産の分け方などもご提案します。
ただ、それらは定められた「ルール」に基づいてのお話です。
それらのルールを無視した処理は決して許してはならないのです。
また、処理の中にはルール違反かどうかがハッキリしないような「グレーな部分」というのも存在します。
今回の事例のケースは、決して法律的なルールは犯してはいませんので、グレーな部分ということができるかと思います。
ただ、今回のケースは、相続税を扱っている税理士にとっては当たり前と呼ばれるような典型的な「名義預金」となるケースです。
私が申告を担当したとしても、おそらく「名義預金なので相続財産に加算する必要があります」と処理したでしょう。
最終的にどう判断するか
今回のケースの場合、いくつかのパターンが存在すると思います。
例えば、
① A税理士の様に、納得のいかない相続人の申告代理を辞退する
② 名義預金として否認(あとで修正申告が必要)されるリスクを説明したうえで、名義預金を相続財産から除く
のようなパターンを想定した場合、税理士としてどちらのパターンを選択するのが正解なのでしょうか。
お客様の満足度を得たいと思えば、②の選択肢をとるほうが賢明かもしれません。
そのほうが相続税の納税も少なくて済みますし、税務調査等で指摘されない可能性もゼロではありません。
ただ、相続税を担当する税理士としては、②の方法をとることが賢明かどうか。
このあたりは税理士によって考え方が変わるかと思います。
自分ならどうするか
今回のケースの場合、考えなければならない要素がいくつかあります。
申告期限まで1ヶ月しかない状況、しかも税理士として最繁忙期である2月に相続税の申告を受任した状況です。
どう考えても納税者に満足のいく説明をしてあげられるだけの時間があったとは考えにくい。
一方的に申告代理を辞退と書いてありましたが、あくまで長女側の主張です。
しかも、この長女の職業は弁護士ということですので、そのあたりを考慮すると相当A税理士は苦悩したのではないかと推測されます。
自分がその立場になった時、どのような対応をするのか、できるのかということを考えさせられた事例です。


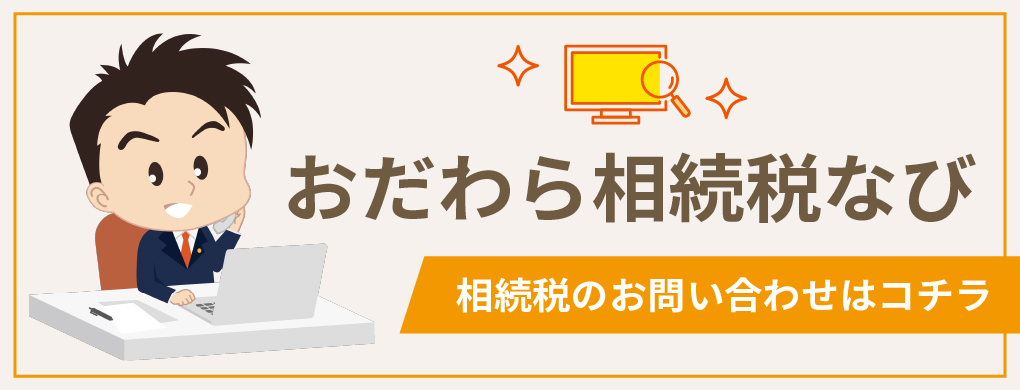
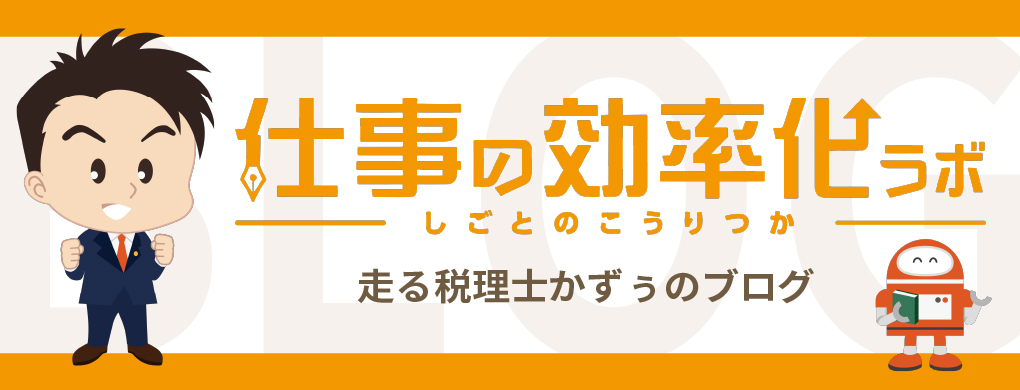
This Post Has 0 Comments