
新司法試験制度が大幅に見直し!現実と理想のギャップ
新聞に「政府が司法試験合格者数の見直しを提言」と言う内容の記事がありました。
数年前に法曹界人口の増加を目指して始まった新司法試験制度ですが、大きく見直される方向に入ったということです。
新司法試験制度が始まった当初は年間3,000人程度の司法試験合格者をだすことを目標としていましたが、この見直しにより当初計画よりも3割以上合格者を減らす方向で調整が入りそうです。
なぜ、このような事態になってしまったのでしょうか。
司法試験制度の大幅な見直し
新聞の記事の内容は下記のようなものです。
法律の専門家を養成する制度の改革について検討する政府の法曹養成制度改革推進室は21日、司法試験合格者数を年間1500人程度以上とする提言案を有識者会議に示した。
政府はすでに3千人程度を目指すとしていた計画を撤回。
提言案は事実上の下方修正とみられ、法科大学院の定員削減や学生募集停止が加速しそうだ。
政府は7月までに適正な合格者数などを提言する予定。提言案によると、改革推進室は企業や自治体などを対象に行った調査結果をもとに、今後も法曹人口を増加させる方針を明示。
「質・量ともに豊かな法曹を養成する」という現行制度の趣旨を尊重し、旧司法試験の合格者数で最多だった約1500人を下回らないよう、法科大学院改革など必要な取り組みを進めるべきだとした。また、法曹資格者の多くが法律に関わる仕事に従事している現状から、これまで輩出してきた1800~2千人程度の合格者数を「相当」と評価。
一方、1500人程度を確保するにあたって「法曹の質の確保を考慮せずに達成されるべきではない」と付言した。司法試験は平成18年から原則的に法科大学院修了者が受験する仕組みを導入。
政府は法曹需要の増加を見込み、年間合格者数3千人程度を目指したが、弁護士の就職難などが問題化し、25年に撤回した。
昨年の合格者は1810人で、受験者数はここ数年、8千人前後で推移している。当初は7~8割と想定された合格率は2割程度にとどまる。
4万人を超えていた法科大学院の入試受験者は今春初めて1万人割れ。
6千人に迫った入学者も2201人まで減った。
開設された74校のうち、25校が学生募集停止を表明。
入学定員は3169人と最大時に比べほぼ半減した。(引用:産経新聞2015年5月22日)
平成18年、「年間3,000人程度の司法試験合格者を生み出す」という内容で新司法試験制度がスタートしました。
新司法試験制度では、原則として「法科大学院」の課程を修了した者に司法試験の受験資格を与えて司法試験を受験してもらいます。
そして、その司法試験に合格した者に司法修習と呼ばれる実務補修を受けてもらい、最後に試験を行って法曹界に入ってもらうという流れになっています。
「司法試験と言う筆記試験だけでは法曹の素質は判断できない。多様な人材を求めるためにも筆記試験だけで判断しない資格制度を作りたい」
このようなニーズから、筆記試験の一発チャレンジではない新司法試験制度が始まったのです。
3つの大きな理想と現実のギャップ
ただ、現実にはうまくいきませんでした。
問題点は多く指摘されていますが、代表的な問題点の例は下記のようなものです。
① 就職先が無い
この制度が始まった趣旨の一つが「法律事務所が少ない(弁護士が少ない)から増やしましょう」というものです。
もともと日本には弁護士が働く法律事務所自体が少なかったんですね
ところが、この制度が始まって司法試験合格者が急増してしまった結果、司法試験合格者が就職できないという状況が出来てしまいました。
法律事務所が少ない → もともと受け入れ先が少ない → 新人が就職する場所が無い
という連鎖です。
政府には「一般企業にも社員として弁護士を必要とする需要があるだろう」と言う見込みがあったようですが、企業が欲しているのは経験豊富な法律家であって、司法試験に合格したばかりの新人法律家ではありません。
そのようなミスマッチにより、「就職できない弁護士」と言うのがニュースにもなりました。
イソ弁(いそうろう弁護士)とかノキ弁(ヒトの事務所の軒を借りて営業する弁護士)とか言われたりもしていました。
見積が甘かったと言われてもしょうがありません。
② 弁護士の数の急激な増加
新司法試験制度への移行により、弁護士の数が急増しました。
平成16年には約20,000人だった弁護士ですが、平成26年には約35,000人にまで増えました。
10年前と比較しても倍近い割合の増加です。
それだけ業務が増えていれば良いのかもしれませんが、仕事がそんなに急に増えるわけありません。
むしろ裁判の数は減っているくらい。
10年前と比較しても、裁判の件数自体は30%ほど少なくなっているそうです
もちろん弁護士の仕事は裁判だけではないと思いますが、客観的な数値としては「むしろ仕事は減っている」と言うことができるかもしれません。
弁護士の方からは、新しく登録する弁護士の数を減らしてほしいという要望が出ていたのです。
③ 法科大学院制度の失敗
法科大学院を創設した当初の予想では、法科大学院修了者の70~80%が新司法試験に合格して法曹界に入れるという見込みでした。
ただ、法科大学院が乱立してしまい、大学院課程修了者の質の低下を心配した実務界の要請により実際の合格者が少なくなってしまったのです。
最終的に司法試験合格率は低迷し、20%台程度となってしまいました。
また、法科大学院を終了しなくても司法試験を受けることができる予備試験制度というものも問題になりました。
法科大学院を終了するためには数百万円の学費が必要となりますが、予備試験であればそれらの学費が不要となります。
しかも、予備試験組の方が法科大学院修了者よりも圧倒的に司法試験の合格率が高かったのです。
もうこうなると、高い学費を払ってまで法科大学院を目指す人が少なくなっていくのは明らかです。
年々、法科大学院の志願者は減少し続けてしまったので、法科大学院自体がどんどんと廃校になっていくという悪循環となってしまいました。
理念は間違っていないと思う
こられらのことが意味することは何でしょう。
理念として「法曹界の人口を増やす」という方向は、決して間違ってはいないと思います。
ただ、「司法試験という資格試験」と言う枠にとらわれてしまったため、様々な要因が絡んでうまくいかなかったというのが現実だと思うのです。
なかなか難しい問題ではありますが、「弁護士の数を増やす」という行為自体が目的となってしまい、「法曹へのニーズを満たす」という本来の目的が薄れてしまっているのではないかなと。
弁護士を増やさなくても、もっと違うカタチでニーズを満たしていけるような気がするのですが…。


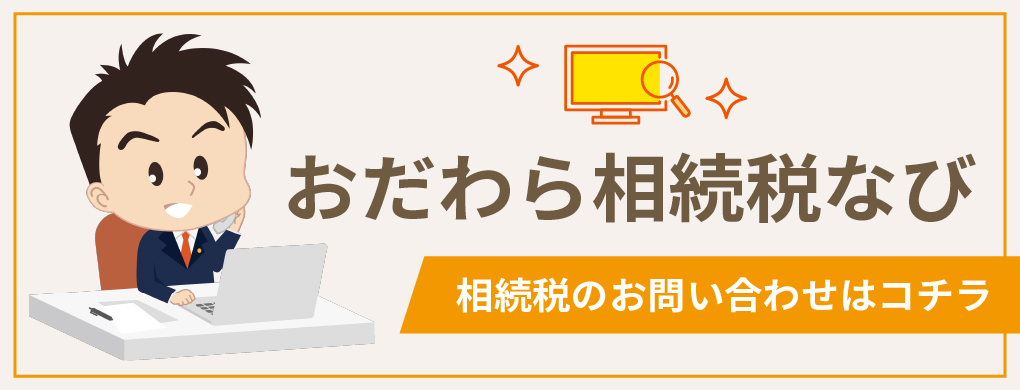
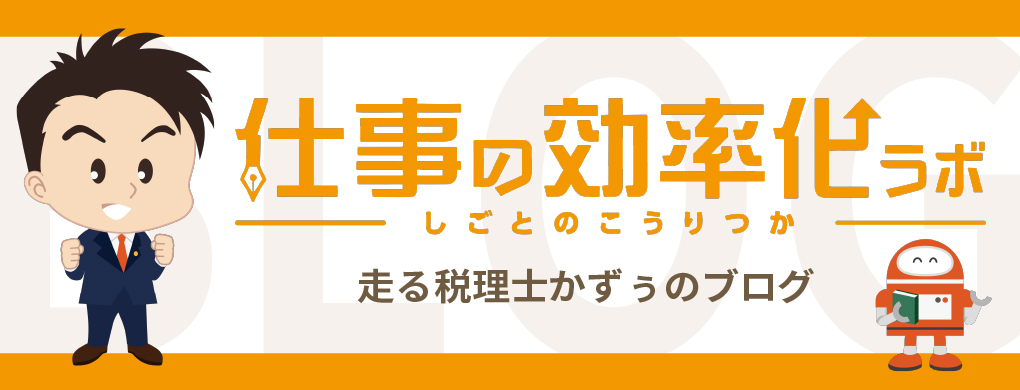
This Post Has 0 Comments