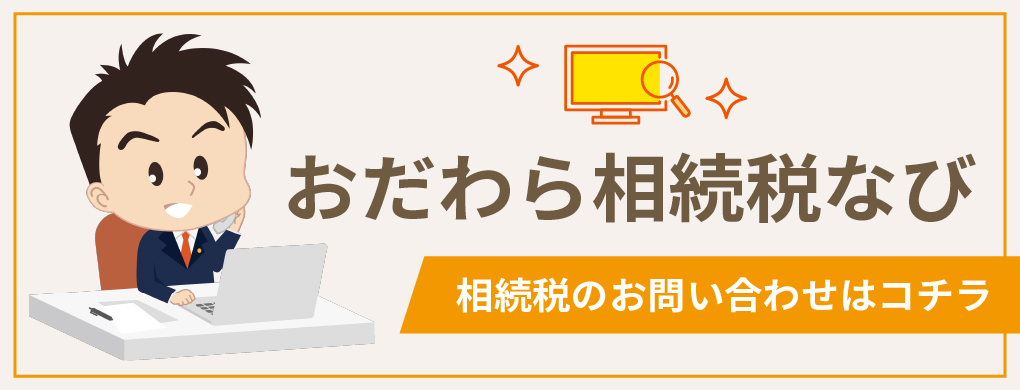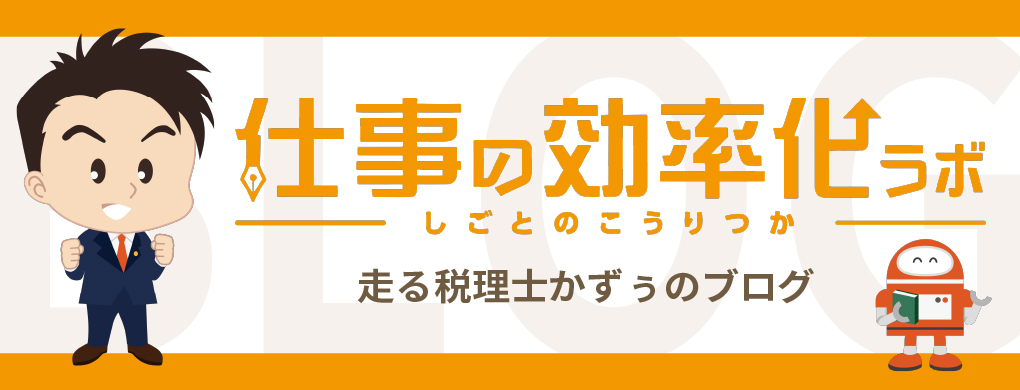事業主や社長に大きな節税メリット「小規模企業共済」
高齢化社会や少子化などにより、将来の年金制度に大きな不安をお持ちの方も多いはず。
30代40代の人たちの中でも、今から老後の生活費対策として貯金や投資などの色々な準備をされている方も多くなってきました。
大企業にお勤めの方である程度の年数を勤めていられれば、それなりの退職金も期待できます。
リタイアしたときに何百万、何千万円も退職金をもらえるような会社であれば、老後の生活資金の計画もだいぶラクになるでしょう。
ただ、そんなものは大企業に勤めている人だけのお話。
個人事業主や中小零細企業の経営者にとって「退職金なんて縁がない」と思われている方は多いのでは?
実は、個人事業主や中小企業の経営者にも国が全面的にバックアップしている退職金に似たような制度があるのです。
その制度とは「小規模企業共済」というものです。
小規模企業共済とは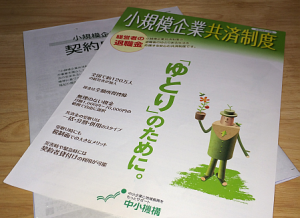
小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者などが、自分の事業をやめたり会社を退職する時などに、それまで積み立てたお金(掛け金)に応じて共済金を受け取れる制度です。
個人事業主や経営者にとっては、リタイアしたときにまとまったお金がもらえるので「退職金」のようなものと思ってもらってよいかと思います。。
この制度を運営しているのは独立行政法人中小企業基盤整備機構。
国が100%出資している歴史のある制度で、現在でも100万人以上の方が加入しています。(ちなみに自分も加入済みです。)
加入するには一定の資格が必要
ただ、誰でもこの制度に加入できるわけではありません。
加入するためには次に掲げるような一定の要件が必要となります。
▼農業、宿泊業や娯楽業、製造業、建設業、運輸業、不動産業で常に使用する従業員が20人以下の会社役員または個人事業主
▼宿泊業・娯楽業以外のサービス業、商業(小売業・卸売業)で常に使用する従業員が5人以下の会社役員または個人事業主
▼上記2つのどちらかにあてはまる個人事業主の事業に関わる共同経営者(個人事業主2人まで)
▼事業に従事または常に使用する従業員が20人以下の企業組合や協業組合の役員
▼農業経営をメインとして行い、常に使用する従業員が20人以下の農事組合法人の役員
▼税理士法人や弁護士法人などで常に使用する従業員が5人以下の士業法人社員
要は個人事業主もしくは中小企業の経営者などが対象となります。
ですので、純粋なサラリーマンやある程度の規模のある会社役員は加入ができません。
ただ、個人事業主の専従者(事業をお手伝いしている奥さんなど)や社長以外の役員さんでも加入できたりします。
また、サラリーマンでも副業や不動産投資を営んでいる方で、それなりの事業規模がある方は加入できたりもします。
このあたりはケースバイケースの判断になるようなので、事前に加入できるかどうか確認してみましょう。
小規模企業共済へ加入するには
小規模企業共済に加入するには代理店窓口で手続きをする必要があります。
主な代理店窓口は銀行や信用金庫ですが、商工会議所や青色申告会、各種業界団体の事務窓口でも手続きできます。
代理店には加入申込書が置いてありますので、必要事項を記入して申し込んでください。
申し込みの際には、個人事業であれば開業届、法人であれば全部事項証明書(登記簿謄本)などが事業を行っていることが確認できる書類などが必要になります。
申し込みから1~2か月程度の審査期間があり、審査が通れば「共済手帳」と「加入者のしおり」がお手元に届きます。これでまずはOK。
掛金は月額1,000円から70,000円まで
小規模企業共済の掛金(保険で言うトコロの保険料)は月額1,000円から加入することができます。
そこから自分の希望で500円ごと増額していくことが可能で、最大で月額70,000円まで加入することが可能です。
初回は基本的に現金支払ですがが、2回目以降の掛金は指定した銀行口座からの引落。
支払方法も毎月払い、半年払い、年払いの3種類から選ぶことができます。
共済金を受け取ることができるのはリタイアした時
小規模企業共済の共済金を受け取ることができるのは、基本的に事業をやめたときや退職した時、または事業を売却した時に請求して受け取ることができます。
途中で解約することも可能ですが、その時には払っていた掛金よりももらう解約金の方が少なくなってしまう(元本割れ)こともあるので注意が必要です。
受け取り方法は一括で受け取る方法のほかに分割で受け取る方法なども選択できますので、請求時の状況に併せて選択することが可能です。
また、契約の途中で契約者が死亡した場合には、ご遺族に対して共済金が支払われます。
死亡に起因して共済金は支払われますが、支払われる共済金は生命保険の取り扱いとは異なりますので注意が必要です(死亡退職金となります)。
小規模企業共済のメリットとデメリット
まず、小規模企業共済のメリットはどのようなものがあるでしょうか。
① 事業主や経営者の退職金の準備ができます
共済金は「退職金」として受け取ることができるので、リタイアしたあとの資金準備ができます。
② 掛金は所得税の節税になる
共済掛金の全額は所得税の控除の対象になるので、かなりの額の節税が見込めます。
年間で最大84万円の所得控除が受けられるのは大きい効果です。
③ 受け取る共済金も節税効果が高い
仮に一括で受け取る場合には、退職所得と同じ取扱いになります。
退職金は税制上非常に優遇されている所得なのでこれを利用しない手はありません。
④ 契約者貸付制度でいざというときの資金対策にもなる
自分が納付した掛金の範囲内であれば、無担保・無保証で融資を受けることができます。
上記のようにメリットも大きいですが、デメリットが無いわけではありません。
例えば、納付期間が1年未満で解約した場合には戻ってくるお金は無く、すべて掛け捨てとなってしまいます。
また、加入期間が20年未満の場合、元本割れしてしまう可能性があります。
ただ、デメリットよりもメリットの方が大きい制度であることは間違いありません。
特に30代40代の世代には非常に効果の高い制度となっています。
次回はどれくらいメリットがあるか、具体例でみていきたいと思います!(*´з`)