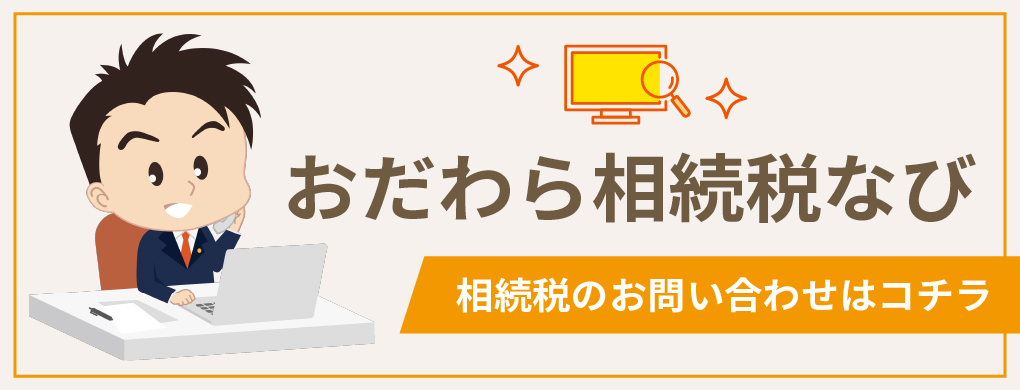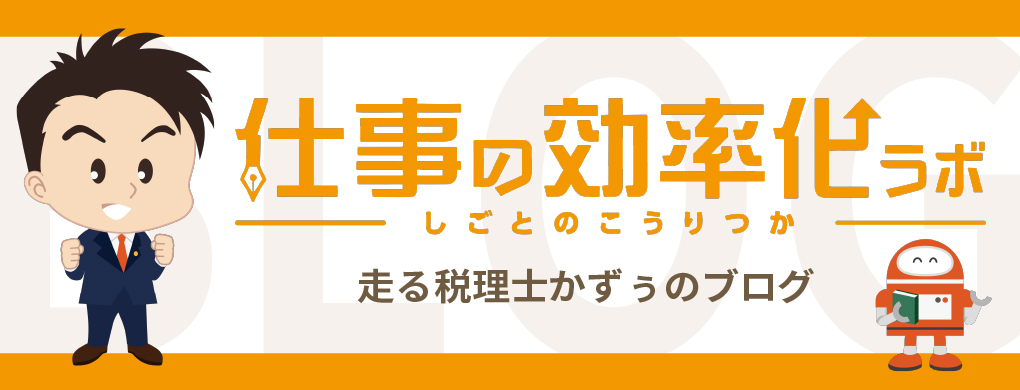スタッフの給料が増えれば節税できる所得拡大促進税制とは?~
長く続いていた緊急事態宣言もいったん終了し、ここからもう一度事業を見直していこうと思われている方も多いはず。
新規スタッフの採用などに向けて動き出した会社も増えてきました。
税制においてもそういった中小企業をバックアップしている制度があります。
それが「所得拡大促進税制」というものです。
所得拡大促進税制とは?
所得拡大促進税制とは、前期と比べて給与などの支払額を増加させた中小企業や個人事業者に対して、その増加した給料の金額の15~25%相当額を法人税や所得税から控除できるという制度です。
従来から「お給料の支給額を増やした場合には税額控除があるよ~」という制度はあったのですが、若干使いにくかったという面があります。
そういった声を反映して、令和3年度の税制改正によってもう少し使いやすい制度に見直されました。
ちなみに制度が延長されたことにより、中小企業であれば令和6年3月31日に開始される事業年度まで、個人事業主については令和6年分までの確定申告で対象となります。
どういった点が改正になったの?
一番大きな改正点は「適用要件が一本化して簡素化された」というところです。
従来の制度では、基本的に前期から今期にかけてずっと在籍していた雇用保険対象のスタッフの給料のみを抽出して計算する必要がありました。
ですので、中途入社した人や退職した人の給料などは一つ一つ確認しながら除いていく必要があったんですね。
この計算が結構面倒くさいので、適用をためらっていた会社が多かったとのです。
今回の改正によって、比較する給与は中途入社や退職などを加味することなく、あくまで前期に支払った給与と今期に支払った給与を単純に比較して増加しているかどうかを判定すればよくなりました。
雇用調整助成金などを受給している会社はもう少し計算が複雑にはなりますが、今までと比べればかなり計算は楽になったと言えます。
特にコロナ対策で給与を抑えていた中小企業も多かったはず。
ここで採用を増やしたりしていこうという企業にとっては非常に使いやすい制度になったと言えるでしょう。

具体的な計算内容はどうなっている?
今回の所得拡大促進税制は、「通常申請」と「上乗せ申請」の2パターンがあります。
(1)通常申請の場合
一般的な通常申請の場合について、概要は次のようになっています。
① 適用するための要件
基準となるスタッフの給料の総額が前年度と比べて3%以上増加していること
② 税額控除
増加した給料の金額に対して15%を法人税や所得税から控除する(上限は税額の20%まで)
例えばですが、前年の基準となるスタッフの給料が800万円、今年の給料が1,000万円だったとします。
そうすると1,000万円-800万円=200万円なので、200万円÷800万円=25%の増加となります。
ですので①の要件は満たすことになります。
要件は満たすので、200万円×15%=30万円が税額控除の金額となります。
(仮に法人税が100万円だったとしたら100万円×20%=20万円が上限になります)
(2)上乗せ申請の場合
上乗せ申請の場合について、概要は次のようになっています。
① 教育訓練費の前事業年度比増加率 ≧ 20%
⇒ 控除率を5%上乗せ
② 継続雇用者給与等支給額の前事業年度比増加率 ≧ 4%
⇒ 控除率を10%上乗せ
(注) ①か②のいずれかだけでも適用可能
上乗せ申請についても要件が緩和されたので、対象になる企業は増えそうです。
税額控除の金額は非常に大きいので、積極的に採用活動を進めたい会社にはぜひ利用してほしい制度です。
いつまでが対象となるの?
この制度の対象となる期間は次のようになっています。
中小企業(法人)・・・令和6年3月31日まで期間内に開始する各事業年度
個人事業主・・・令和6年までの確定申告

注意しておきたいポイント!
この制度の適用にあたっては次のポイントを注意しておくようにしましょう。
ポイント① 給与には役員や親族への給料は含まない
この制度の対象となる給料は、基本的にスタッフへの給料が対象となりますので、役員報酬や事業専従者などの給料は含まれません。
正社員だけではなく、賃金台帳を作成しているパートやアルバイトの給料も含めたところで計算できます。
ただ、使用人兼務役員であったり役員の親族など一定の人の給料は対象外になるので注意しましょう。
ポイント② 助成金などについては控除した後の金額で計算をする
雇用調整助成金などの受給をしている場合には、控除額の計算などをする際に助成金の額を控除する必要があります。
ポイントは「実際に会社負担がどれくらいあるのか」というところになりますので注意しましょう。
ポイント③ 事前準備が必要
上乗せ措置を受けるためには、計画的な教育訓練の実施や経営力向上計画の策定が必要です。
手続きには時間がかかりますので、余裕をもって計画を策定するようにしましょう!
まとめ
所得拡大促進税制についての概要を説明しました。
少しでも分かりやすくするため、記事の内容については用語の説明など簡略化していますのでご容赦ください。
実際の申請手続きや計算にあたっては、国税庁や経済産業省のホームページなどを参照してください。