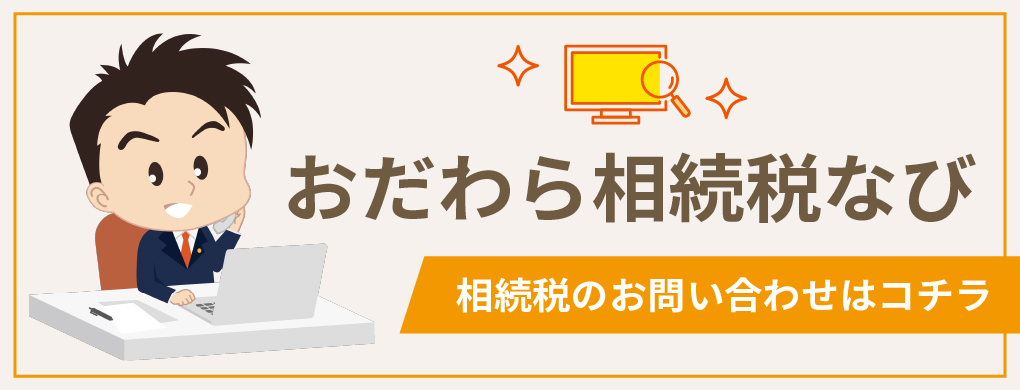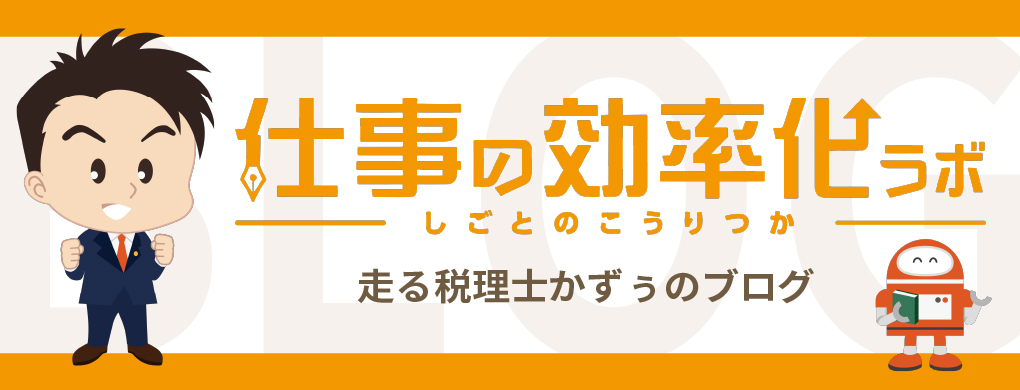認知症の相続人がいる場合には早めの対策を!

相続の現場には色々なトラブルがつきものです。
その中で最近よく聞くトラブルは「相続人の中に認知症の方がいる」というケースです。
相続人に認知症の方がいると手続きが大変
相続が起きると、亡くなった方の奥様も高齢であるケースが多いのですが、やはり高齢になると認知症の症状がある方も少なくありません。
認知症の症状の程度にもよりますが、もしそのような症状がある場合には「成年後見制度」という法律的な手続きをとって後見人を選任して頂くのが原則的な方法となります。
そして裁判所で選任された後見人と一緒に遺産の分割などの相続手続きを進めていくことになります。
ただ、そのような手続きが必要になるということを知らない方も多いです。
また、例え知っていたとしても、成年後見制度には弁護士などの手続き費用も必要になりますし時間もかかります。
「何とかなるだろう」と放置していると大きなトラブルの原因となります。
認知症と分かった場合には早めの対策を
そのまま遺産分割の相続手続きを進めていき、相続登記など司法書士などの第三者の意思確認が必要な手続きをする際、認知症であったことが発覚するとそれ以降の手続きを進められなくなってしまいます。
そもそも、認知症の方に意思能力はありませんので遺産分割協議自体も無効になってしまいます。
そうなってしまうと最初から相続手続きをやり直さなければなりません。
このような場合、相続税の申告が必要で無ければまだ良いのですが、もし相続税の申告手続きが必要である場合は大変です。
相続税は「相続の開始があることを知った日から10ヶ月以内」に申告・納付しなければならないからです。
相続税には「配偶者の相続税額の軽減」や「小規模宅地の特例」など納税者に有利になるような特例が多くありますが、これらの特例の適用を受けるためには期限内に相続税の申告をする必要があります。
もし期限までに分割が出来ない場合には、一定の届出をしておかないと特例を受けることができません。
相当時間がかかることを覚悟して
 認知症がどの程度進んでいるかの面接や鑑定、裁判所の予約など、成年後見制度を適用する場合には様々な準備が必要です。
認知症がどの程度進んでいるかの面接や鑑定、裁判所の予約など、成年後見制度を適用する場合には様々な準備が必要です。
手続きを開始してから成年後見人が選任されて動き始めることができるようになるまでに相当の時間がかかります。
本来必要でなかった手間が増えてしまったり、最悪のケースではもともと必要が無かった税金まで払う可能性もあるのです。
このようなトラブルを防ぐためには、早めにどのような手続きが必要となるか把握しておくことがポイントです。
相続手続はご家庭の事情によって千差万別ですので、まずは専門家に相談されることをオススメします。