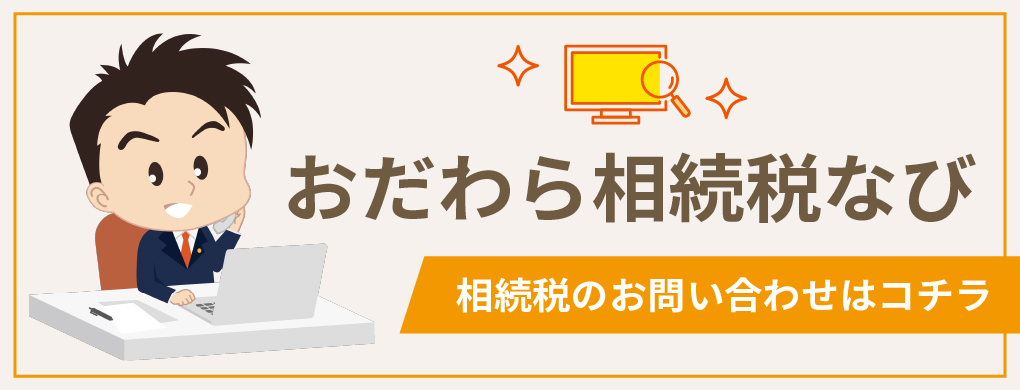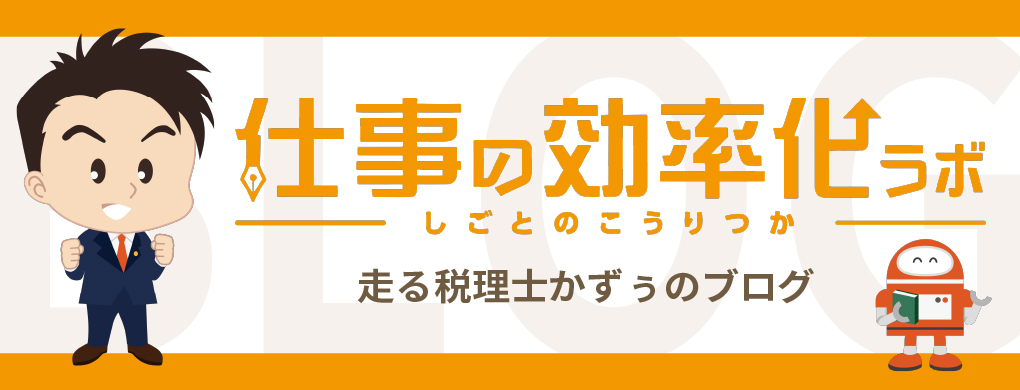税金と社会保険では「扶養」の対象が違うのです
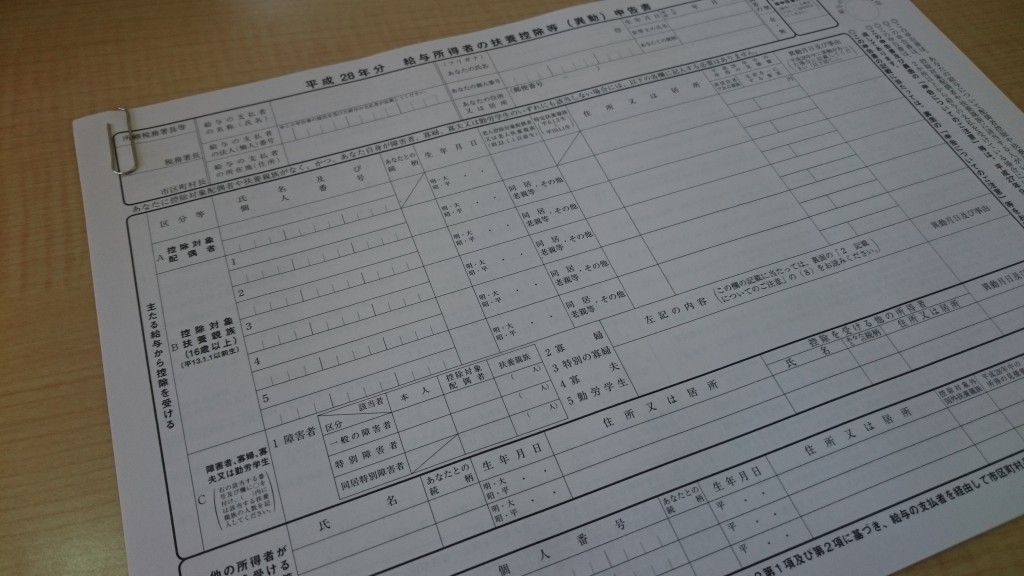
11月に入り、いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。
先日、小田原税務署でお客様分の年末調整用紙をがばっと貰ってきたので、挨拶がてら配りにまわろうと思っています。
今年はマイナンバーの件もあるので、そのあたりも説明をさせてもらいながら配ろうと思っています。
まだまだ不明な部分も多い制度ですので、一つ一つ確認をしながら進めていきたいと思います。
年末調整の処理をする際、お客様からいろいろと相談を受けます。
その質問の中でも多いのが「扶養」に関する件です。
中でも勘違いしていられるのが「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違いについて。
この点について少しおさらいをしておこうと思います。
よくある家庭を例として考えてみよう

例をあげて考えた方が分かりやすいので、下記のように前提条件を作っておきましょう。
▼家族はサラリーマンのご主人(社会保険加入、年収600万円)、パートの主婦、20歳の大学生の息子の3人
▼ご主人の所得税の税率は20%
このようなケースの場合、税金上も社会保険上においても、奥様や息子はご主人の「扶養者」となっていることが多いかと思います。
その方が家計全体での負担が少なくなりますからね。
奥様も息子さんもご主人の扶養から外れないように、パートやアルバイトの収入を調整しているのではないでしょうか?
では、どの段階まで扶養でいられるのか考えてみます。
税金の扶養は「年間のトータルの収入」で判断
まず税金の扶養の範囲について説明していきましょう。
よく「103万円の壁」などと表現されますが、ここで言う103万円とはお給料収入、つまりアルバイトやパートさんの収入の場合の金額を指します。
ご主人が奥様を扶養しているとした場合に受けられるのが「配偶者控除」です。
奥様の年間パート収入が103万円未満であればこの控除が受けられますので、ご主人の所得から38万円を控除することが出来ます。
ご主人の所得税の税率が20%だとすれば、年間で7万6千円ほど税金が少なくなる計算です。
結構大きい金額ですよね。
奥様の場合、もしパート収入が103万円を超えてしまっても141万円未満までであれば「配偶者特別控除」を受けることが出来ます。
配偶者控除よりも控除額が減ってしまいますが、例えばパート収入が130万円未満であれば受けられる控除額は16万円。
ご主人の税金にすれば3万2千円ほど税金が少なくなります。
ただ、奥様自身も所得税や住民税が発生しますので、家計全体でみればもう少し影響は大きいかも。
大学生の息子さんの場合に受けられるのが「扶養控除」です。
配偶者控除と違い、扶養控除はアルバイト収入が103万円未満でなければ受けることは出来ません。
1円でも超えてしまえばアウトです!
通常の扶養控除は38万円ですが、19歳以上23才未満の大学生などの場合は特定扶養親族というモノに該当します。
控除額は63万円に跳ね上がりますので、年間で12万6千円も税金が少なくなります。
大学生の子供を持っている親は、子供がいくらアルバイトで稼いでいるのか把握しておきましょう!
間違えて申告すると、あとで経済的にも精神的にも大ダメージを受けます。。。(;´Д`)
これらの配偶者控除も扶養控除も、それぞれの収入は「1月1日から12月31日までの給料の金額の合計額」で判定されます。
ですので年末調整の用紙に扶養情報を記入する際には、あくまで見込み額に基づいて判断することになります。
103万円ギリギリで働いていると、12月の給料次第で控除額が変わってしまうコトは良くあります。
ある程度、奥様や息子さんがどの程度収入があるか把握しておくようにしましょう。
もし超えてしまった場合には、あとで税務署から「所得税の是正通知」なるものがお勤めの会社に届きます。
所定の手続きに基づいて税金を納めなければならなくなりますので注意しましょう。
社会保険の扶養は「見込み額」で判断
税金に対し社会保険のほうはどうでしょうか。
社会保険においては、よく「130万円の壁」などと表現されますが、これも給料の収入金額に基づいているものです。
ただ、社会保険の場合は税金とちょっと違っています。
よく「年間の給料収入が130万円を超えると扶養から外れて自分で社会保険を払わなけらばならない」と勘違いされています。
実はこの130万円というのは、「年間の見込み収入額」を意味しています。
実際の社会保険の扶養への加入要件は「年間を通して130万円未満の収入しかないコト」で、実際には月ごとの収入で判断します。
1カ月当たりの基準金額は108,330円。
例えば、奥さんが6月からパートで働き始めたとして
6月分給料 120,000円
7月分給料 130,000円
8月分給料 120,000円
だったとしましょう。
仮にそのまま年末まで働いたとしても、年間トータルでは130万円未満になるかもしれませんが、毎月の収入は基準となる108,330円を超えています。
ですので、このような場合にはご主人の社会保険の扶養要件には該当しないのです。
また別の例として、正社員として働いたが3月に結婚を機に退職。6月からパートで働き始めたとします。
3月までの社員としての給料 1,000,000円
6月分給料 80,000円
7月分給料 80,000円
8月分給料 80,000円
このようなケースの場合、年間トータルでは130万円を超えてしまいますが、毎月の収入は基準額以下です。
ですので、このような場合には退職した後からご主人の社会保険の扶養に入ることが出来るのです。
税金の扶養と社会保険の扶養は違う
 また税金の扶養と社会保険の扶養は別に考えることが出来ます。
また税金の扶養と社会保険の扶養は別に考えることが出来ます。
例えば、大学生の息子さんについて、税金についてはご主人の扶養に入れたとしても、社会保険については奥様の扶養に入れることが可能です。
ご主人が個人事業主である程度収入があり、奥様が社会保険加入事業所してお勤めしている場合などは、税と社会保険を別に考えた方が有利になることがあります。
色々なパターンを考えると「扶養」については正直キリがありません。
自分の家庭がどのパターンに当てはまるのか、年末調整を機会にもう一度考えてみてはいかがでしょうか。